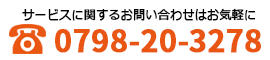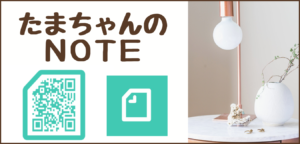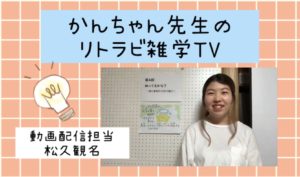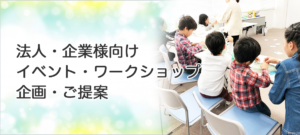余白のすすめ
ぎちぎちに詰め込むと学力は伸び悩み
来週からの定期テストに向けて、私立組の中高生が頑張っています。
それぞれに頑張っている部活との両立で、睡魔と戦いながらのテスト対策。
テストの期日は前もって決まっているので、逆算しながらコツコツと進めていた子と、部活が停止となる1週間前から初めてギアチェンジする子との差は「余白」を持ち合わせているか否かがキーポイント。
日常生活においても、大人にも子どもにもこの余白部分は大きな差となりますね。
テスト前の学習計画を提出してもらうと一目瞭然。
「予備日」とか「調整日」なる項目が記載されている子は、自分のことを良く理解していて、自分なりの「余白」をきちんと準備しています。
逆に、ぎちぎちの計画表を提出してくる子は、本当に実行できるかどうかの確認が浅く、テスト前1週間だけが連日の一夜漬け。
いつもこの状況だと、記憶の引き出しにしまっておくことは難しくなってしまいますね。
自分が実行できる、余白のある計画表が立てられるように、まずは考えて欲しいと思っています。
自己コントロールの仕方を学ぶ
もちろんテスト対策も大切ではありますが、中高生においては、まず「自分なりの自己管理法」を見つけてもらうことが最優先です。
部活のある日や習い事のスケジュールは、ひとりひとり違っているので、自分の予定を念頭において無理なく進め、実行していく力を磨くために中間、期末定期テスト前の過ごし方を身につけて欲しいと思っています。
どんな時でも余白は必要。
頭の中を整理する作業が上手い子は、余白活用が上手で、例外なく成績を伸ばしています。
中高生が伸びてくる時
自分の学習方法に自信が持ててくると、集中して問題に取り組めるようになってきます。
当然、集中力も高まり、正答率もぐんぐん上がってきます。
「やる気スイッチ」は初めからどの子にもあるわけではありません。
自分なりの進め方を色々試しているうちに、しっくりくる進め方を見つけることが出来てきます。
説明を聞いている時は、理解をした気になってはいますが、自分の中で定着理解したわけではありません。
中高生には、問題のドリル数も課す必要があります。
今日も理数の担当教師と、うなりながらのテスト対策が続いています。
次へつながるオリジナルの学習方法を見つけて欲しいと思っています。