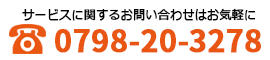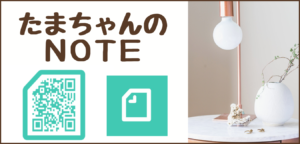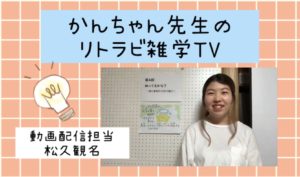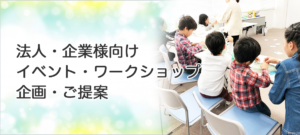春の気配を感じながら
まもなく新しいスタートの予感
2月に入り、立春も過ぎたというのに、寒波到来などで気温の下がる日も多く、三寒四温の季節を迎えています。
身体も心も慣れるのに懸命・・といったところでしょうか。
しかし、子どもたちは現学年の最終章に入っていて、4月から始まる1学年あがった新たなフィールドを見据え、学年末テストに向けて頑張っています。
学力向上も大切な要素のひとつではありますが、まずは心身ともに元気で生活していくリズムを整えることを、優先して欲しいと思っています。
具体事例で伝えることが出来る子どもへ
子どもたちと話していると、人の話にきちんと耳を傾けられる子は、自分の思いを伝えることも上手だと痛感します。
お友だちとの言い合いの場面。
Aさんは、「今日学校で、○○さんに△△と言われたけど、謝ってくれない。」
Bさんは、「○○さんに△△と言われて、すごくイヤな気分になった。」
Cさんは、「○○さんが△△と思っているみたいだから、まずはそう思った理由を聞かせて欲しい。」
ひとりずつに、「何があったのかな」と聞いてみたのですが、3人の答えは少しずつ違っています。
Aさんは、すでにこの時点で、悪いのは相手だという前提。
Bさんは、自分の気持ちを伝えていますね。
Cさんは、自分の話を聞いてもらう機会が多く、聞いてもらっているお話の中で、「その時お友だちはどんな気持ちがしていたんだと思う?」などの声かけをもらっている機会が多いのではないかと推測され、相手の心情を聞こうという姿勢が表れています。
話をきちんと聞いてもらうことに慣れている子どもは、自分の感情を論理だてて整理して、話すことが上手です。
一方、聞いてもらえる機会の少ない子は、自分の言い分をひたすら訴えてきます。
自分の話を聞いてもらいたい!!が常に心の大部分を占めているので、まずは何よりも自分の気持ちを聞いて欲しくて仕方がありません。
よく話しを聴いてもらっている子は、相手の気持ち(心情)をくみ取るゆとりが違っています。
まずは話が聞ける・・を優先したい訳
聞く・話す
どちらも大切であることに間違いはないのですが、優先順位としては「聞く習慣」が先に定着して欲しいと思っています。
相手を思いやる気持ちは、相手の気持ちをイメージできるかどうかが大切なポイント。
それには、様々なジャンルの経験豊富な子どもが、やはり頭一つ抜け頭角を表してきます。
公園でわいわいがやがやと喧嘩しながら遊んだ経験。
キャンプに行った自然の中での発見。
外で身体を動かしヘトヘトになるまで走り回った記憶。
図鑑片手にセミの抜け殻を興味深く観察した。etc・・・。
様々な経験を通して、自分の引き出しに取り入れて記憶している子は、相手の気持ちを聞いた時、そのイメージを捉え表現する豊かな広がりを持ち合わせていて、相手の立場に立って物事を判断する力に優れています。
聞く力=じっくり話をきいてもらった経験の数
この公式を忘れないでいたいですね。
聞いてくれる人のところに人は集まる
「聞かせたい!」思いが強い人は人を集める作業に余念がありません。
聞いてくれる人のところには、自然に人が集まるのです。
それは子どもだけではなく、大人も同じなのではないでしょうか。
よく話しを聞いてね!は、よく話を聞いてあげてね!がセットになっています。
子どもとの関わりを通して、大人が学ぶことの方が意外にも多いことをお忘れなく・・。
4月からの新スタートを前に、2月、3月は子どもの周りの大人が聞き上手になりたいですね。