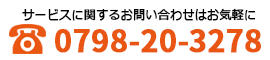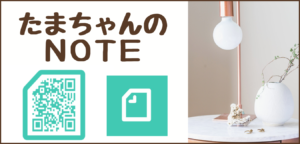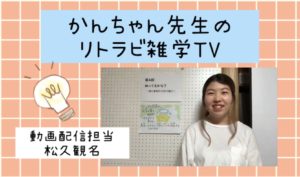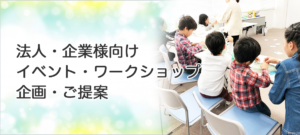待てる大人との関りで子どもは成長する!
気持ちの切り替え
秋晴れの土曜日。
いかがお過ごしですか。
絶好の運動会日和でしたね。
子どもの笑顔がはじける瞬間に立ち会えるのは、嬉しい限りですね。
今日は、そんな秋の日に大人の気持ちの切り替えについて、少し。
大人の感情的な対応が
その場しのぎの子どもを生み出すという現実
大人が感情的に叱ったり怒ったりしている時は、受け取る子ども側も感情的になったまま、その時を過ごしています。
注意を促したいときに、感情を抑えきれない・・というような態度や表情で接していると、子どもは注意された内容について全く考えは及ばず、早くこの場を通過したい!という気持ちだけでいっぱいになっています。
「通過」なのです。
当然同じことは何度も繰り返すことになります。
なぜ、注意するのか・・。
物事の良し悪しを考えてもらって答えを見つけて欲しい・・という気持ちで注意をするのなら、何度も繰り返す苛立ちなどの思いを声を荒げて伝えても、子どもが自ら考えるきっかけにはなりません。
「伝えたいのなら伝わるように・・。」
これは子どもも大人も共通で、まずは自分自身(注意する側)が相手に伝わる言葉で冷静な状態で伝えることが最優先です。
子どもが落ち着くまでは、「待ってるね」が魔法の言葉
その場で腹が立ったその瞬間に言葉を伝えるとどうしても威圧的で強い口調になってしまいがち。
そんな時はまず少し冷静になれるまで時間をおいてから伝えたい趣旨を話しましょう。
結論(例えば○○してはいけない・・)と伝えるよりは、どうして○○してはいけないのかなあ・・と考える時間を与える伝え方をしてみませんか。
「少し待ってるから、どうしてかわかったら教えてね」
これぐらいの言葉を投げかけて、待てる大人になりたいものです。
直ぐに結論や答えを教えてしまっては、その物事の良し悪しを自分が本当に理解していなくても、
「わかった。」
「ごめんなさい」
と、いとも簡単に子どもはその場を通過する術をマスターしてしまいます。
これをマスターした子どもは、その後ありとあらゆる注意される場面で、このマスターした術を本当に見事に使いこなす達人へと変身してしまいます。
考える体験の不足は高学年以降の大きな差となって表れる
物事にはいつも理由があることを考えることが出来るようになれば、必ず他者に対しての思いやりの心が育まれます。
近年、お友だちと触れ合う機会が減少していて、かかわり方が分からずトラブルになるケースも増えてきています。
時代に応じた学び方も必要ですが、生きていくための必要な土台形成は幼少期からの継続したかかわり方で積みあがることを忘れないでいたいですね。
※食欲の秋、久しぶりに娘手作りの餃子をおなかいっぱいいただきました♪
リフレッシュできたので、また秋を満喫していきたいです
美味しいものでいっぱいの秋。
自分に余裕が生まれるように、ぜひあなたなりの楽しみ方を見つけてくださいね!