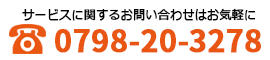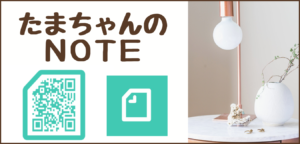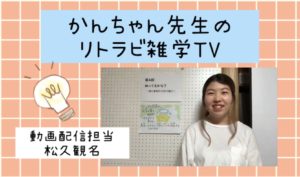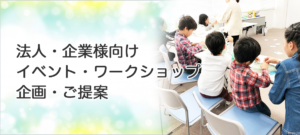考え抜く力
10月22日(月)
私達のまわりは、日々進化しています。
その変化に順応しながら、自分らしく生きる方法をそれぞれが考え生活しています。
教室で子供たちを見ていて、最近特に感じることがあります。
それは、与えられることに対してはなんとか適応しながら進めるのですが、自分で課題を見つけることが、極端に出来なくなっているということです。
いつも授業のスタートは百マス計算などから、始まります。
当然、タイムに個人差があり、いつも早く終わる子供たちにはすぐに計算のプリントを裏返しにして、文章問題作りが課せられています。
1つの文章題で「+と÷」を使う文章問題2題・・などと、その日の条件にあった文章問題を作らなければなりません。
文章問題が出来上がれば、線分図か問題の絵をかいてもらっています。
取り組みを始めてしばらくは、みんな四苦八苦・・。
「先生、問題難しくてもいいから、解く方がいい・・。」などと、声があがっていました。
なんとかやっとの思いで考えた自分の問題を線分図や絵で表すことが出来ないからです。
みんなが作った問題は回収して、授業中みんながその日の単元の問題を解いている時間を利用して、
すぐにそのままプリントに打ち出し、1枚の文章題プリントとして作成し、
またみんなは他の人が作った問題を解くことになります。
問題として、成立しているものもあれば、成立していないものもあるのですが、そのままの形でプリントにしています。
解いていくうちに、
「先生、③番って、解ける?問題の聞きかたおかしくない?」などと、子供たちから?が点灯します。
?と感じた場合、どのように修正すれば良いのかを書いてもらっています。
私達教える側がすべきこと。
いろいろな考え方はあるとは思いますが、私は出来るだけ子供たちに考えさせる時間を提供することだと
思っています。
ベースを作り、それを生かせる力へと結びつけることが出来てこそ、ワンランク上へとまた
アップしていけるのではないでしょうか?
子供たちを考えることが出来る人材へ・・・。
次世代を担う子供たちへ今、本当の意味でサポート出来ることを大人が考えていきたいですね![]()