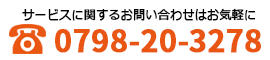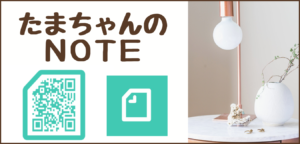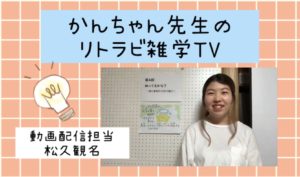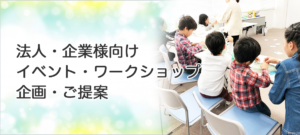イメージする時間
5月29日(金)
【目をとじて 思い描いて 考える】
様々なものをイメージする力は、生まれながらに持っているものだけではありません。
あらゆるシーンで、子どもたちがよく経験してきたごっこ遊び。
幼い頃は、お医者さんになりきったり、お母さんになりきったりと、見よう見まねでよく遊びましたね。
そのものをイメージする力。
では、イメージ力はどうして個々に大きく異なるのでしょうか。
何年も子どもたちのすぐそばで関わって来た私の所見ですが、お母さんの接し方がイメージ力を育む上では、大きな意味を持っているように感じています。
たとえば、幼い子に信号の見方を教える時。
「赤は止まれ、黄色は注意、青は進めだよ。」
「ちゃんとよく見て横断歩道は渡ろうね。」
こんな風に教えるお母さんが多いですよね。
でも、
「信号って、どうして3つの色があるのかな。」
「みんなどんな風に渡ってるかちょっと見てみようか・・。」
こんな風に問いかけるのはどうでしょう。
少なくともそう言われた子どもは、信号を渡る人たちが、どの色の時にどんな風にしているかと観察し始めるに違いありません。
しばらく観察したのち、
「もし、赤の時に渡ってしまったら、どうなっちゃうのかな・・・。」
こんな質問をしてみたら、子どもはどうなるかと頭の中でイメージし、想像し、そして危ない事に気づくのではないでしょうか。
些細な事でも考えさせる工夫が、大人側には必要だといつも感じています。
「先生、家の子は想像力が乏しくて・・。」
「どうしてなんでしょうか。」
こんな風に相談されるケースがよくあります。
でも、見方を変えれば想像力が乏しいのではなく、想像を働かせて考える場面が与えられていなかった・・という事も言えるかもしれません。
教える事は簡単です。
でもただ良い事、悪い事を教える事が大人の役わりなのでしょうか。
大人と子どもの一番の違いは経験数の違いです。
大人は自分が経験済の事だから、すぐに答えを教える事に慣れてしまっていませんか。
一個人の我が子の存在を尊重し、考える作業を数多く経験させる事で、イメージ力は親の領域をはるかに超えて広がりをみせるに違いありません。
そう考えると、なんだか楽しみですね♪♪